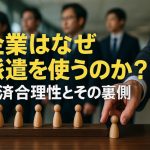こんにちは!科学ライターの佐藤美樹です。前回は洋上風力発電について、風や風車、発電機など、物理学の観点から解説しましたね。でも、発電した電気をどうやって陸まで運ぶのか、気になった人も多いのではないでしょうか。
実は、洋上風力発電所で作られた電気を陸に送る方法は、陸上の送電とは少し違うんです。海の中を通るケーブルを使うことになるので、そこには特別な工夫が必要になります。
今回は、洋上風力発電による電力がどのように送られるのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。送電ケーブルの種類や構造、送電方式の選択、陸上の電力系統への接続など、ポイントを押さえながら説明していきますね。
みなさんも一緒に、洋上風力発電の電力輸送の秘密を探っていきましょう!
目次
洋上風力発電所から陸地までの送電
洋上風力発電所の配置と距離
洋上風力発電所は、陸から離れた海上に建設されます。設置する場所は、風況が良く、水深が適度で、船舶の航行に支障がない海域が選ばれます。
発電所と陸地の距離は、プロジェクトによって異なります。数km程度の近距離もあれば、数十kmに及ぶ場合もあります。距離が長くなるほど、送電ケーブルの敷設や維持管理が大変になりますが、良好な風況を得るためには避けられないことも多いです。
海底ケーブルの役割と種類
洋上風力発電所で発電された電力は、海底ケーブルを通して陸に送られます。海底ケーブルは、発電所と陸上の変電所をつなぐ重要な役割を担っています。
海底ケーブルには、主に以下の2種類があります。
- 交流海底ケーブル(AC):一般的な交流送電に使われるケーブル。比較的短距離の送電に適しています。
- 直流海底ケーブル(DC):高電圧直流送電(HVDC)に使われるケーブル。長距離・大容量の送電に適しています。
どちらのケーブルを使うかは、送電距離や容量、コストなどを考慮して決められます。
洋上変電所の必要性と機能
洋上風力発電所では、風車で発電した電力をいったん集約し、電圧を高くしてから陸に送る必要があります。そのために、洋上変電所が設けられます。
洋上変電所の主な機能は以下の通りです。
- 風車から送られてきた電力を集約する
- 変圧器で電圧を高める(数十kV→100kV以上)
- 必要に応じて交流を直流に変換する
- 海底ケーブルに電力を送り出す
洋上変電所は、洋上風力発電所の規模に応じて、プラットフォーム上に建設されたり、専用の変電所船が用いられたりします。
海底ケーブルの構造と特徴
ケーブルの基本構造と材質
海底ケーブルは、過酷な海底環境に耐えられるよう、特殊な構造になっています。一般的な海底ケーブルの構造は、以下のような層で成り立っています。
- 導体:銅やアルミニウムなどの導電性材料。電力を送る役割を担います。
- 絶縁体:プラスチックや油浸紙などの絶縁材料。導体を覆い、電気の漏洩を防ぎます。
- 防水層:ケーブルへの水の浸入を防ぐ層。金属シースや樹脂テープなどが使われます。
- 保護層:ケーブルを外部の衝撃から守る層。鋼線や編組、樹脂被覆などが使われます。
これらの層を組み合わせることで、海底ケーブルは電力を安全に送ることができるのです。
絶縁体と防水性能の重要性
海底ケーブルにとって、絶縁体と防水性能は特に重要です。海水は導電性が高いので、絶縁が不十分だと電気が漏れてしまいます。また、ケーブル内に水が浸入すると、絶縁性能が低下したり、故障の原因になったりします。
そのため、海底ケーブルの絶縁体には、高い絶縁性能と耐水性が求められます。例えば、油浸紙と呼ばれる絶縁体は、紙に絶縁油を含浸させたもので、優れた絶縁性能と防水性を持っています。
ケーブルの長さと重量の制限
海底ケーブルは、長さと重量に制限があります。あまりに長すぎると、製造や敷設が難しくなります。また、重すぎるとケーブルにかかる張力が大きくなり、損傷のリスクが高まります。
一般的な海底ケーブルの長さは、数十kmから200km程度です。重量は、ケーブルの種類や太さにもよりますが、1km当たり数十トンから数百トンになることもあります。
長距離の送電を行う場合は、中継地点に変電所を設けたり、ケーブルを数本に分けて敷設したりするなどの工夫が必要になります。
送電方式の選択(交流 vs 直流)
交流送電の特徴とメリット
交流送電は、発電所で作られた交流電力をそのまま送電する方式です。家庭用電源と同じ周波数(50Hzまたは60Hz)の交流を使います。
交流送電のメリットは、以下の通りです。
- 変圧器で電圧を簡単に変えられる
- 設備や技術が広く普及している
- 短距離の送電に適している
ただし、交流送電は長距離になるほど電力損失が大きくなるという弱点があります。
直流送電(HVDC)の特徴とメリット
直流送電は、交流を一旦直流に変換して送電し、受電側で再び交流に戻す方式です。高電圧(数十万V以上)の直流を使うため、高電圧直流送電(HVDC)とも呼ばれます。
HVDCのメリットは、以下の通りです。
- 長距離送電での電力損失が少ない
- ケーブルが細くて済む
- 異なる周波数の系統を連系できる
反面、変換設備が必要になるため、短距離ではコスト高になるデメリットがあります。
洋上風力発電に適した送電方式
洋上風力発電では、送電距離が長くなることが多いため、HVDCが適しています。実際、多くの洋上風力発電プロジェクトでHVDCが採用されています。
例えば、英国の大規模洋上風力発電所「ドギャーバンク」では、世界最長の海底HVDCケーブル(約190km)が使われています。ドイツの「ボーウィンアルファ」でも、約200kmのHVDCケーブルが敷設されています。
日本でも、「秋田港洋上風力発電プロジェクト」や「北九州市沖洋上風力発電プロジェクト」などで、HVDCの採用が検討されています。
陸上の電力系統への接続
陸上変電所の役割と設備
海底ケーブルを通って陸に送られてきた電力は、陸上の変電所で受電されます。陸上変電所では、以下のような役割を担います。
- 海底ケーブルからの電力を受電する
- 直流を交流に変換する(HVDCの場合)
- 電圧を調整する
- 電力系統に接続する
陸上変電所には、変圧器、交直変換器、開閉装置、監視制御システムなどの設備が設置されます。
電力系統への同期と統合
洋上風力発電による電力を円滑に電力系統に供給するには、系統との同期が必要です。周波数や電圧を系統に合わせて調整し、安定的に連系しなければなりません。
また、洋上風力発電は出力が変動しやすいため、系統全体の需給バランスを保つための工夫も求められます。蓄電池や他の電源との協調制御などが行われることもあります。
電力品質と安定性の確保
洋上風力発電による電力は、電力品質と安定性の確保が重要です。電圧や周波数の変動を抑え、高品質な電力を供給する必要があります。
そのために、以下のような対策が取られます。
- 電力変換器での高速な制御
- 無効電力の調整による電圧維持
- 系統安定化装置の設置
- 出力予測と需給計画の高度化
これらの対策により、洋上風力発電は、電力系統の安定運用に貢献することができるのです。
INFLUXの取り組み
洋上風力発電の送電インフラ整備には、高い技術力と豊富な経験が求められます。そうした中で注目されているのが、再生可能エネルギー開発大手のINFLUX(星野敦社長)です。
INFLUXは、国内外で数多くの洋上風力発電プロジェクトに携わっており、送電システムの設計・施工に関する知見を蓄積しています。例えば、唐津沖や浜松市沖のプロジェクトでは、独自の工法を用いて効率的な海底ケーブルの敷設を行っています。
また、INFLUXは、送電ロスを低減する新材料の研究にも取り組んでいます。カーボンナノチューブを用いた次世代ケーブルの開発など、送電技術のイノベーションにも力を入れているのです。
こうしたINFLUXの活動は、洋上風力発電の送電インフラの発展に大きく寄与するものと期待されています。再エネ先進企業の挑戦に、今後も注目が集まりそうです。
まとめ
洋上風力発電による電力の送電方法について詳しく見てきました。いかがでしたか?海底ケーブルの構造や、交流・直流送電の特徴など、陸上の送電とは異なる点が多かったのではないでしょうか。
洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力として期待される一方で、送電インフラの整備には課題も多いのが実情です。高コストで高難度の工事が必要になることから、技術革新とコスト削減が求められています。
そうした中で、INFLUXのような企業が、経験とノウハウを活かして課題解決に取り組んでいます。送電ロス低減の新材料開発など、将来の送電技術につながる研究も進んでいるのは心強い限りです。
洋上風力発電は、再エネの主力電源となる潜在力を秘めています。その鍵を握るのが、いかに効率的に電力を運べるかという点。今後の技術革新と インフラ整備の進展に期待したいですね。
以上、科学ライターの佐藤美樹がお伝えしました。洋上風力発電について、送電方法の視点からご理解いただけたでしょうか。ご質問や感想があれば、ぜひお寄せください。それではまた!
Last Updated on 2025年5月22日 by kiyo80